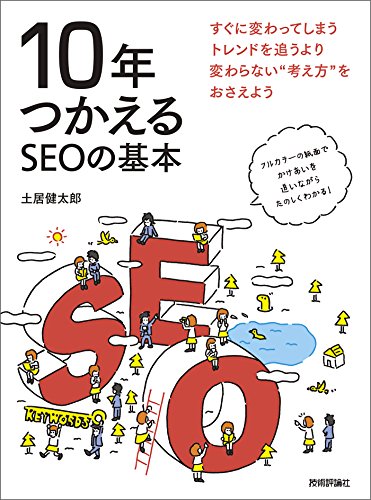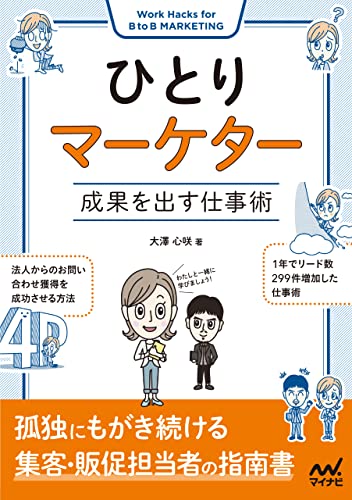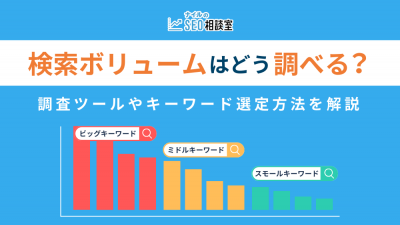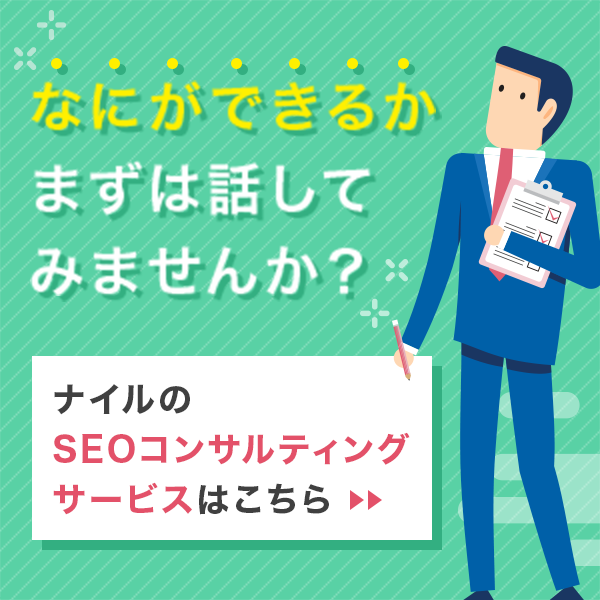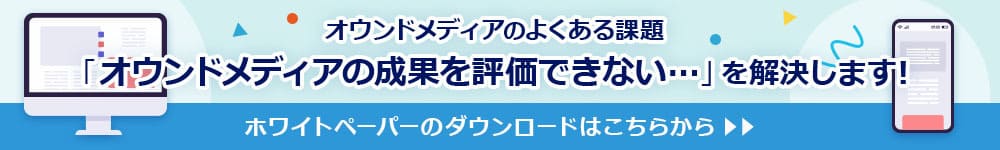インタビューの三原則【コンテンツづくりの三原則 第13回】

オウンドメディア運営において、コンテンツづくりは最大の肝です。「コンテンツづくりの三原則」では、毎月1つのコンテンツづくりのテーマや目的を取り上げ、そこに紐づく3つのトピックを深掘りしていきます。
第13回は「インタビューの三原則」。写真や絵で何かを表現する際に重要な「光」「影」「角度」。実はこの3つの要素は、インタビューの際にもあてはめられるものなのです。
\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/
目次
「陰翳礼讃」の世界を構成する光と影
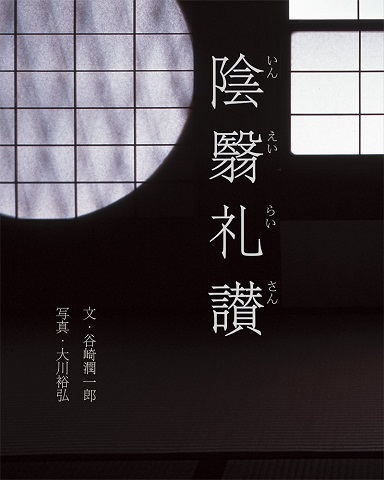
谷崎潤一郎の随筆「陰翳礼讃」をご存じでしょうか。まだ、日本に電灯がなかった時代、障子や廁(かわや)、行燈(あんどん)など、和の生活様式に見られる陰翳(いんえい:光のあたらない暗い部分)に日本の美を見いだした作品です。
「陰翳礼讃」は、安藤忠雄、大竹伸朗、ロバート・キャンベルといった建築家やアーティスト、文化人たちにも多大な影響を与えてきたといわれます。私の友人にも「陰翳礼讃」に影響を受けてカメラマンになったという人がいます。写真撮影は、まさに谷崎がこだわり続けた「光」と「影」と「角度」によって「陰影の美」を表現する格好の手段だからです。
では、谷崎がこだわり続けた「陰影の美」とは、どのような世界なのでしょうか。
私自身、幼少期に暮らした祖父母の家は、中庭に面した厠に行く暗い廊下を通るのに、随分怖い思いをした記憶があります。木々に覆われたしっとり薄暗い中庭は、昼間でさえ、もののけが出てきそうな不気味な雰囲気でした。

しかし、大人になってから訪れる祖父母の古屋敷の高い天井や黒光りする廊下、裸電球の色温度の低いやわらかい光が演出する陰影は、いつの間にか風情のある心地良い風景となっていました。そんなことを、あらためて気づかせてくれたのが「陰翳礼讃」でした。
そして、雑誌やウェブで制作の仕事に携わり、インタビューの経験を重ねるうちに、写真とインタビューには、「陰翳礼讃」を構成する共通項があることに気づきました。
実は「光」と「影」と「角度」という写真を構成する3要素は、インタビューにおいても必須の条件であると知ったのです。
「光」をあてなければ何も見えない

数年前、女優の広瀬すずさんがテレビで「どうして生まれてから大人になったときに、照明さんになろうと思ったんだろう?」というコメントをして炎上したことがありました。
その批判の主な理由は、「照明さんの仕事をバカにしている」ということ。しかし、これは女優という華やかなステージに立つ広瀬さんにとっては、ごく素朴な疑問だったと思います。ですから、彼女が非難されるのはちょっとかわいそうな気がします。
女優さんが輝くためには、やはり「光」をあてる人が必要不可欠です。光がなければ女優さんはその存在すら認識されません。女優さんの存在を生かすも殺すも、ライティング(照明)次第といえるでしょう。
まだ、誰からも撮られていない角度から、最も魅力的に映る表情を捉えるべく、光をあてる。そして、出来上がった素材をどんな順番で並べ、どのように編集していくかを考える。
インタビューでもその考えは同じです。インタビュアー(取材者)は聞き手である以上に、インタビュイー(取材対象者)を、光を操りながら照らす“照明係”でなければなりません。
インタビューにおける「光の強弱」とは?
カメラマンが撮影の対象に対して、光を駆使するのに対し、インタビューでは光の代わりに言葉を使います。晴天の直射日光のようなストレートな質問、曇天の拡散光のような遠回しの質問。このような使い方が、インタビューをするときに求められるスキルなのです。
光は、暗すぎても明るくすぎてもいけません。インタビューにおいて「光が暗すぎる」というのは、「肝心なことを何も聞いていない」ということです。一方、「光が明るすぎる」というのは、欲張りすぎて、通り一遍のことしか聞いていないということです。
一番退屈なのは、正面から強い光をフラッシュで焚く照明です。これは、免許証やパスポート、履歴書などに使う証明写真の撮影のようなもの。合同記者会見の写真撮影もそうです。インタビュイーの正面に光がフラットにあたるため、陰影がまったくありません。真正面からのフラットな写真ほど味わいがなく、おもしろくないものはありません。
「影」を作ることで見えないものを映し出す

影をどう作るか、どう消すかも、ライティングの重要なスキルです。つまり、「見えない」ものをいかにして見せるかという作業です。
影を作ることによって、高級感や落ち着き、深み、重厚さ、立体感を表現することができます。また、背景や輪郭に影を作ることで、時間やドラマを作ることができます。
最近のウェブメディアでは、SNSに象徴されるように、短くシンプルで白黒がはっきりしたフラットな表現があふれています。陰影のグラデーションで表情を作る重厚なコンテンツは、あまり好まれていないように感じます。
情報の消費のされ方が、スマートフォンをベースにしたつまみ食いになっているため、できるだけシンプルでフラットなコンテンツが好まれるのかもしれません。しかし、それ以上に、陰影を帯びたコンテンツを創作するには、高度なテクニックが求められることも一因ではないでしょうか。
証明写真が、短いシャッタースピードで自動でも簡単に撮影できるように、フラットで陰影やボケ、グラデーションのないシンプルなコンテンツを作ることは簡単です。ですから、安い原稿料で質の低いコンテンツが量産されるのも無理はありません。
しかし、そういったコンテンツは、読者に価値を与えているでしょうか。示唆に富んだ味わい深い情報を提供できているでしょうか。それこそ、「陰翳礼讃」のように、読んだ人の人生に強い影響を与えるような爪痕を残すことはできるでしょうか。
山部赤人の和歌で知る表現方法
日本最古の和歌集として知られる「万葉集」には、約4,500首の和歌が収められていますが、「目に見えないことをいかに暗示的に表現するか」が、名作と呼ばれる基準だといわれています。
例えば、下記の和歌。
田子の浦ゆ 打ち出でて見れば 真白にそ 富士の高嶺に 雪は降りける(山部赤人)

「田子の浦を通って出て見るとまっ白に富士の高嶺に雪が降っていたことだ」(講談社文庫「万葉集 全訳注原文付(一)」)には、空が晴れていることにはふれていませんが、「真白にそ」という言葉から、鮮やかな白さに感動している様が描かれ、背景が同系色の白(曇天)ではないことが容易に想像できます。つまり、「見えない」空の色を暗示することで、雪の白さを強調しているのです。
真夏の陽射しがギラギラ輝く海で、あなただったら何を撮影するでしょうか。きっと、太陽を反射する海やまっ白な砂浜にレンズを向けるのではないでしょうか。
あるいは、遠くに見える水平線を挟んで、樹木の影を写してみるとどうでしょうか。暗い場所からチラッと見える深緑は、これから目の前に開ける景色を期待させます。実際に太陽は写っていなくても、日陰と海の水平線があることで強い太陽をイメージさせ、夏の印象を強く表現することができると思います。

WIRED初代編集長が教える「良い質問」とは?
インタビューをするときも、インタビュイーの陰影を演出することで、初めてその人のリアルな人生観、価値観、本音、性格、感情、才能、魅力が伝わってきます。インタビュイーの体験からしか語れないことや、聞かれることでインタビュイー自身が発見するような質問が、私は「陰影」のある良い質問だと考えています。
アメリカのIT雑誌「WIRED」の初代編集長で、ジャーナリストのケヴィン・ケリー氏の著書「〈インターネット〉の次に来るもの 未来を決める12の法則」(NHK出版)に、そんな「陰影」のある良い質問の定義について書かれた章がありますので、一部を抜粋してご紹介します。

・良い質問とは、正しい答えを求めるものではない。
・良い質問とは、すぐに答えが見つからない。
・良い質問とは、ひとたび聞くとすぐに答えが知りたくなるが、その質問を聞くまではそれについて考えてもみなかったようなものだ。
・良い質問とは、思考の新しい領域を創り出すものだ。
・良い質問とは、予想もしない質問だ。
・良い質問とは、さらに他の良い質問をたくさん生み出すものだ。
インタビュアーが正解を持っていて、それを尋ねるだけなら、なかなかその先には進めません。インタビュイーも、これまで何度も同じ質問をされているので、条件反射で答えられるでしょう。その回答には、新鮮味も驚きもありません。
つまり、予定調和や出来レース――「あ、そうですか。なるほど」で終了です。わざわざ会って聞かなくても、メールやアンケート用紙で済みます。
反対に、質問をされて、インタビュイーが即答できないときは、「何それ?そんなこと突然聞かれても知らないよ」となる緊張感も生まれますが、「そういえば考えたことなかったなあ。確かにそれは疑問だ。うーむ。ちょっと考えさせてくれ」と、インタビュイーにとっても新たな気づきとなる可能性も秘めています。これが、「見えない陰影」の発見です。
このように、インタビューにおいて光と影を捉えることは、とても重要だといえるでしょう。
「角度」を変えて陰影をつける
レンブラントという画家をご存じでしょうか。歴史上、最も偉大な画家の一人ともいわれる、17世紀に活躍したオランダの画家です。

絵画や写真の世界には、彼の名を冠した「レンブラントライト」という言葉があります。これは、斜め上からの光で人物を照らし出す手法のことをいいます。
被写体の斜め後ろから半逆光の照明をあてることで、立体感を印象深く強調でき、被写体をより美しく表現するとされています。基本的には人物の鼻筋に対して、上方斜め45°から光をあてます。
また、オランダにはもう一人、フェルメールという偉大な画家がいます。「光の魔術師」と呼ばれる彼は、レンブラントに影響を受けた画家の一人です。
フェルメールの有名な「真珠の耳飾りの少女」は、左上からの光で顔が美しく照らされ、その後ろにあるターバンの影によって立体感が強調されています。このように、平面ではなく立体で物事を捉えるという絵画の手法を確立させたのがレンブラントなのです。

オランダ語の独特な表現「ヘゼリヒ」
彼らが生まれ育ったオランダには、「ヘゼリヒ(Gezellig)」という独特の言葉があります。日本語にすると「心地良い」、英語なら「cozy」に近い言葉ですが、オランダ人は「心地良い」とも「cozy」とも違うと主張します。それは、オランダに暮らす人にしか実感できない、幸福なひと時を表す言葉のようです。
春の優しい陽射しの中のまどろみ。あるいは、夏の長く明るい白夜のやわらかい太陽。気心の知れた友人や家族と過ごすカフェの語り合いのひと時。そんな貴重な光との戯れの時間を、「ヘゼリヒ」というそうです。
オランダは、年間を通して曇天が多く、日照時間が非常に短い国です。夏は白夜になるので夜10時くらいまで明るいですが、一日中夕暮れのようなやわらかい斜光に包まれています。だからこそ、人々にとって、陽射しがとても貴重でありがたいものだとされます。
レンブラントやフェルメールの絵画には、そんな光に対しての憧憬や愛着の思いが反映されているようにも見えます。彼らの描く光と影の優しい世界は、まさにこの「ヘゼリヒ」な瞬間を切り取った1コマです。

手間がかかるから新しい発見や深みがある
インタビューは、まさにレンブラントやフェルメールのように、インタビュイーの人生の1コマを抽出して描き出す作業だといえます。
光を照射する角度を考えながら、光の濃淡や強弱、グラデーションを描いてインタビュイーの魅力を引き出すことは、手間がかかる遠回りの作業です。ですが、手間がかかるからこそ、そこに新しい発見があり、深みが生まれてくるのです。単純な一問一答なら、アンケートやメールで済んでしまいます。
谷崎潤一郎は「陰影礼賛」で、西洋文明の輸入によってフラットになってしまった日本家屋を嘆く一方で、旧来の和の世界の不便さも承知しています。和風建築の家屋の畳や木の廊下、廁、障子は、掃除の手間がかかり、いかにメンテナンスが大変であるかについても綴っています。しかし、和式家屋がすべて電灯と鉄筋とタイルになってしまったら、わびもさびも深みもなくなってしまうと嘆いているのです。
谷崎は「陰影の美」を象徴するものとして、羊羹の半透明の色の美しさを讃えています。
あれを塗り物の菓子器に入れて、肌の色が辛うじて見分けられる暗がりへ沈めると、ひとしお瞑想的になる。人はあの冷たく滑かなものを口中にふくむ時、あたかも室内の暗黒が一箇の甘い塊になって舌の先で融けるのを感じ、ほんとうはそう旨くない羊羹でも、味に異様な深みが添わるように思う。

光と影が、互いに緊張感を持って微妙に絡み合い、光の差し込む角度によってさまざまな姿を現す。そんな手間がかかる演出があるからこそ、羊羹からも立体感、シズル感、触感、温度感、食感、味が伝わってくると感じるのです。
さまざまな角度から光を照射し、さまざまな強弱、濃淡のある陰影を演出することで、初めてインタビューをするその人の歩んできた歳月の光と影、人生観、価値観、本音、性格、感情、才能、魅力が伝わってくるのです。
\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/
関連記事