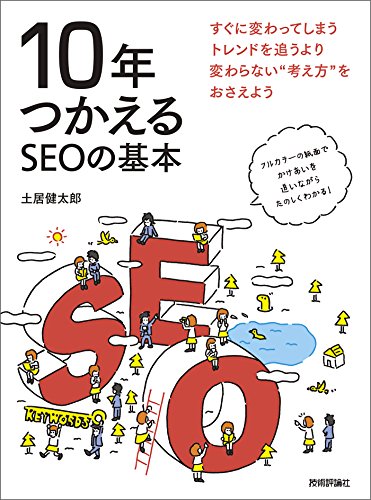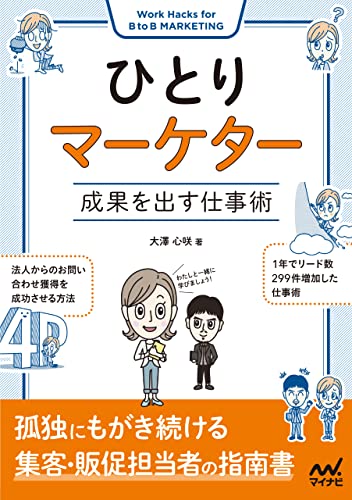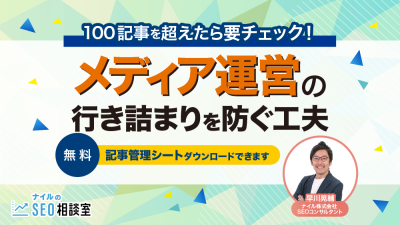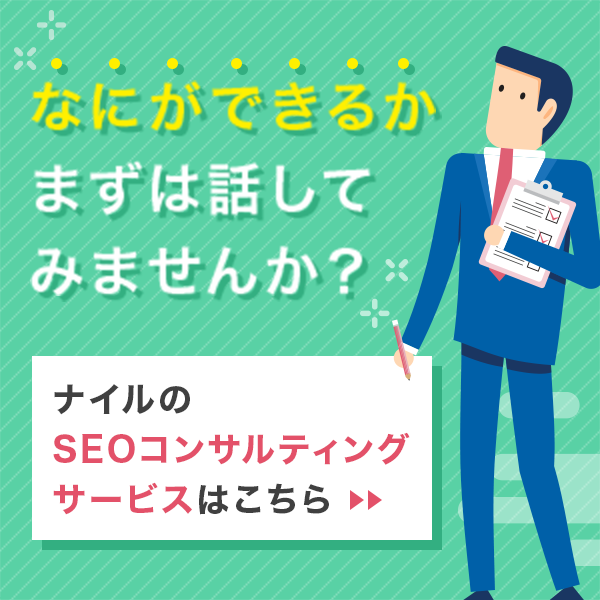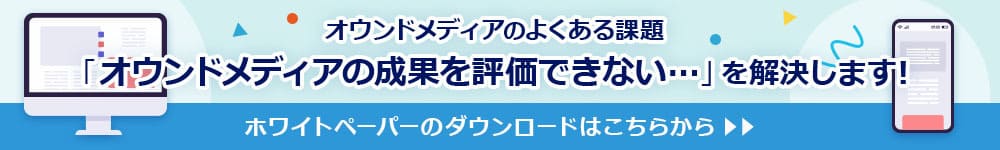モノ・コト・トキの三原則【コンテンツづくりの三原則 第11回】

オウンドメディア運営において、コンテンツづくりは最大の肝です。「コンテンツづくりの三原則」では、毎月1つのコンテンツづくりのテーマや目的を取り上げ、そこに紐づく3つのトピックを深掘りしていきます。
第11回は「モノ・コト・トキの三原則」について解説します。
\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/
目次
モノの価値の変遷

戦後、復興を遂げた1950年代後半の日本では、豊かさの象徴として、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が「三種の神器」と呼ばれました。高度成長期の1960年代半ばには、カラーテレビ、クーラー、自家用車の「3C」がこれに代わっています。そして、平成になって、デジタルカメラ、DVDレコーダー、薄型大型テレビのデジタル家電が「新・三種の神器」と呼ばれたそうですが、これを実感する人はほとんどいないのではないでしょうか。
確かにテクノロジーは日々進化し、私たちの生活を豊かにする象徴だったモノは数多く誕生してきました。しかし、今やほとんどの人に取って手にできるのが当たり前のモノに。機能や価格だけで、その価値を訴求するのが難しくなり、差別化が難しくなっています。成熟した社会において、モノの価値はその機能や価格だけでは決められなくなってしまったのです。
マーケティング1.0~4.0でのモノの価値
「マーケティングの神様」として知られる経営学者のフィリップ・コトラー氏によると、モノの価値の変遷は、マーケティング1.0~4.0に分類できるそうです。
- マーケティング1.0(1900~1960年代)
モノをたくさん安く売れば売れる - マーケティング2.0(1970~1980年代)
モノを選べる時代になり消費者主導に変化 - マーケティング3.0(1990~2000年代)
モノの価値だけでは売れない時代へシフト - マーケティング4.0(2010年代~)
顧客を感動させて忠実な推奨者にする
1900年代後半からは、モノが市場にあふれはじめ、その価値も少しずつ変わってきましたが、基本的にはモノの存在価値は、企業の商品力とマスメディアを使った宣伝力によるところが大きかった時代です。
しかし、インターネットが浸透してきた2000年代に入ってからは、それまでの機能や価格だけに依存したブランディングでは、もはやユーザー(消費者)の心に響かなくなってきました。そして、スマートフォンの浸透した2010年代からは、その傾向はますます加速していきます。
ユーザーは、いつでもどこでも欲しい情報をみずから入手できるようになったため、企業が発信する一方的な広告・宣伝だけに依存しなくなりました。
マスメディアから流れるひとつの情報だけでなく、さまざまな角度からの情報が入手できるため、判断基準は自分の感覚やセンスに合うメディアやSNS、レビューなどのコミュニティーに依存してきています。同時にユーザーは、自分の体験や感想、意見を発信して、周囲から共感されることでモノの価値を決めていきます。
つまり、企業がユーザーとエンゲージメント(信頼関係)を築くためには、信頼する人がどう評価しているのか、どれだけ人にシェアしたい内容なのかといった、ユーザーコミュニティーの文脈に入れるかどうかがカギを握っているというわけです。
これが、モノからコトへのシフトです。
モノ消費からコト消費へシフトした背景

経済産業省の「コト消費空間づくり研究会 取りまとめ」によると、コト消費は下記のように定義されています。
「コト消費とは、製品を購入して使用したり、単品の機能的なサービスを享受するのではなく、個別の事象とが連なった総体である“一連の体験”を対象とした消費活動のこと」
コンテンツマーケティングが台頭してきた背景にも、このモノ消費からコト消費へのシフトがあります。
かつてのように、企業の都合による一方通行の情報を送るだけでは、ユーザーにモノの価値は伝わりません。ですから、企業はユーザーが何を求め、何を体験したがっているのかというユーザー視点で情報を発信しなければならなくなりました。それが、コンテンツマーケティングが普及してきた背景でもあります。
そして、その拡張機能として発達したのが、SNSやレビューのようなコミュニティー機能です。ここから主導権は、企業からユーザーに移ったといえます。
もちろん、今日でもマスメディアを使った広告が、多大な影響力を持つのは事実です。しかし、テレビ、新聞、雑誌、ラジオといった4大マスメディアを担っていたメディアの広告収入は、すべてインターネットに市場を奪われました。
また、若者たちのテレビ離れも加速しており、テレビで活躍するタレントもYouTubeやTwitter、InstagramなどのSNSを無視できなくなっています。これらのSNSを通して、個人の体験価値でモノが語られるようになると、企業の価値は、企業からの一方通行の情報だけでは成立しません。ユーザーと企業が共創しながら、築き上げていくように変わってきています。
ストーリーの構築が重要に
商材は、ユーザーが購入するまでは、単なる機能と価格を備えた無機質なモノでしかありません。しかし、購入されたときからユーザーとの共有体験が始まります。
その体験を想像させるのがストーリーです。こうした、モノ消費からコト消費へ興味・関心が移るユーザーの心をつかむために、重要になってくるのがストーリーなのです。
その商品を購入したらどうなるのか?ユーザーに広くシェアをしてもらうためには何をすべきか?それを知るためには、企業は企業都合の一方通行からユーザー視点に頭を切り替え、ストーリーを構築しなければなりません。
企業のストーリーの語り部は企業自身ですが、企業がユーザーに伝えたいと思うストーリーの主人公は、企業ではありません。
多くの企業は自社の商材のアピールに躍起になるあまり、一方的な主張をしがちです。しかし、ユーザーが自分の求める情報を好きなように取捨選択できる時代に、闇雲に一方的な自己主張だけをしても、ユーザーの耳には届きません。もちろん、心も動かされないし、共感もしてもらえないでしょう。
企業がユーザーに認知され、商材を購入してもらいたいと思うのであれば、まずユーザーの立場になって「心が動くストーリー」を用意しなければなりません。企業のマーケティングの成功は、ユーザーが描くストーリーに、企業が描くストーリーを重ね合わせられるかどうかにかかっているといえるでしょう。
そこに、企業とユーザーの理想的な関係構築が見えてきます。ユーザーが商材を手にして良かったと思う頻度が増えるほど、ユーザーの体験や経験の満足度は上がります。企業は、ユーザーが商材を手にしたことで始まるすばらしいストーリーの体験を、サポートし続けるのです。
コト消費からトキ消費へのシフト

そして2010年以降、コト消費の先に台頭してきたのがトキ消費です。トキ消費とは、博報堂生活総合研究所の提唱した概念で、音楽フェスやハロウィンのような、「その日」「その場所」「その時間」でしか体験できない消費行動のことを指します。
「おしゃれなカフェのケーキを食べにきた」といった、ちょっとした小さな体験もトキ消費に含まれます。
トキ消費を考えるときに参考になるのが、「興奮転移理論」です。これは、ある状況から生じた生理的興奮が、その状況とは直接関係ない別の状況にも影響を及ぼすという理論です。つまり、人は興奮状態にあるとき、周りにある事象への感情も大きく刺激されてしまいます。
皆さんも、大好きなミュージシャンやアイドルのライブに行って、記念にノベルティグッズを買った経験はあるのではないでしょうか。旅行先で買うお土産もそうでしょう。旅先で「ここでしか買えない!」と興奮して買ったものの、後で冷静になると「なんであんなモノ買っちゃったんだろう?」と後悔したことがあるかもしれません。
例えば、アメリカ最大のスポーツイベントといわれるスーパーボウルの広告料は30秒で500万ドル(約5億円)以上ともいわれています。そして、世界有数の大企業は、毎年その広告枠を狙ってしのぎを削ります。
この広告枠を狙うのはもちろん、視聴率が高いということもありますが、イベントによって興奮が高まった状態で商品を視聴することで「興奮転移」が働き、イベントで高まった興奮状態が商品への感情に「転移」される点に価値が見いだされているのです。これは、オリンピックやサッカーワールドカップも同様です。
キアヌ・リーブス主演の大ヒット映画「スピード」では、いくたびの危機を乗り越えた主人公の男女が最後に恋に落ちてハッピーエンドで終わるのですが、このときにサンドラ・ブロック演じるヒロインが「極限状況で始まった恋は長続きしない」と不安を述べるシーンがあります。
これはまさに、同じ刺激的な「体験」をすることで興奮状態になったとき、お互いのことが「好き」という感情に転移されることを象徴したセリフです。相手のことを「好きだ」という感情が、刺激的な体験とともに、気づかないうちに強化されたのです。

相手が「楽しい」「おもしろい」「興奮した」と感じる刺激的な「体験」を提供することが、ブランディングには重要になります。刺激的な「体験」とブランディングは、密接に関係しているのです。
トキ消費の体験が企業プロモーションの軸に
現在、インターネットでどんな商品も、簡単に買える時代となりました。ネットのほうが商品はずっと豊富ですし、24時間いつでも購入できます。そんなオンラインショッピング全盛の時代にあってもなお、先進的な企業はリアル店舗に積極的に力を注いでいます。
イオンモールが、リアルな体験や体感、人が集うコミュニティーの場「ハピネスモール」を目指し、展覧会や公演などさまざまなイベントを開催するのも、刺激的な「体験」を提供することで、ユーザーとエンゲージメントを高めるためです。
ただお店が集まっていて買い物ができる場所ならば、ネットショップでも構いません。ショッピングモールが、ただの「買い物ができる場所」から「思い出に残る楽しい体験ができる場所」へとシフトを図っているからです。

さらに、トキ消費の例としてよく挙げられるのが、渋谷のハロウィンや年末年始のカウントダウン、サッカー日本代表の応援といったイベントです。
人々が仮装したり、応援したりするためだけに見知らぬ人といっしょになって渋谷駅前のスクランブル交差点に集まるのは、トキ消費の象徴的現象だといえます。

AKB48選抜総選挙や握手会を使ったプロモーション、映画「この世界の片隅に」のクラウドファンディングによる製作資金の調達、キングコングの西野亮廣氏がオンラインコミュニティを軸に仕掛ける絵本や映画、ゴミ拾い、街づくりなども、まさにトキ消費の成功例です。
エンターテインメント業界に限らず、商品やサービスの持つ「(社会的)価値」に共鳴し、商品の購入を通じて自然環境へ貢献したり、地域活性のためにサービスを利用したりする消費行動も、トキ消費といえるでしょう。
トキ消費を利用したプロモーション活動例
近年、アンテナ感度の高い企業は、マーケティングやプロモーションのために、トキ消費を積極的に活用しています。
トキ消費を利用したプロモーション活動例を、いくつか見てみましょう。
- サントリー食品インターナショナル株式会社
サントリー食品インターナショナル株式会社は、2018年の「ペプシ Jコーラ」のキャンペーンで、いち早くTikTokの撮影手法を取り入れて制作・配信したダンス動画を公開。それをまねした多くのユーザーが、TikTok上に動画を投稿しました。 - ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社は、2018年に「恋のはじまりは放課後のチャイムから」というドラマ動画を配信。ドラマに登場するキャラクターがそれぞれSNSアカウントを持っており、ユーザーにそのアカウントをフォローしてもらい、ドラマの世界に入り込んだかのような気分になってもらう施策を行いました。 - ハイアールジャパンセールス株式会社
家電メーカーのハイアールジャパンセールス株式会社は、「#恋する家電(ハイアール)」という動画プロモーションの第1弾を、2018年に実施。有名な声優が家電役になってしゃべり、一人暮らしの生活にツッコミを入れるというストーリーの動画を、SNSでユーザーにリツートやリポストしてもらい、150万回再生されています。 - Beats
アメリカでオーディオ機器といえば、BOSEやJBLが有名ですが、2000年代になるとBeatsという新興のオーディオメーカーが頭角を現し、あっという間に大人気ブランドになりました(現在はApple傘下)。
Beatsは、ヒップホッププロデューサーのドクター・ドレーを中心に設立されたブランドです。Beatsはライブのスポンサーになったり、音響機器を提供したりすることで、音楽ライブの象徴的ブランドになりました。これも、ライブで興奮状態になったとき、「楽しい」という感情はイベントを主催した企業へと転移された結果といっていいでしょう。楽しい感情とともに、その企業のことを「好きだ」という感情が強化されたのです。テニスプレイヤーの大坂なおみ選手が試合前に耳にしていたのもBeatsの製品ですが、これもスポーツ体験とワイヤレスイヤホンが同期したワンシーンといえます。
このように、モノ消費からコト消費、そしてトキ消費へのマーケティングの変遷は、ユーザーが「所有」という目に見える価値よりも、「体験」という目には見えない価値をより重要視する時代への変遷といえるでしょう。
トキ消費にある3つの特性
トキ消費には、下記の3つの特性があるといわれます。
- 非再現性
その瞬間を逃したら、二度と同じ体験はできないというリアルタイム性や希少性。 - 参加性
当事者として、主体的にイベントへコミットしていく姿勢や意識。 - 貢献性
イベントの目的や達成目標を仲間とともに分かち合い、いっしょに貢献している自覚。
企業は、商材だけで差別化するのは難しくなったので、商材を通して社会にどのように貢献していきたいのか、どのような価値観を持っているのかをユーザーに伝えて、共感してもらうことが重要となりました。
コトラー氏が示したマーケティング4.0は、「ユーザーが商品を通して自己実現できるか」ということが重要になってきていることを意味します。
今は、コロナ禍によってリアルイベントの開催は難しくなっていますが、トキ消費はオンラインを通じて加速しているようにも見えます。

モノからコトへ、コトからトキへ
イソップ寓話に、「3人のレンガ職人」という労働にまつわる有名な教訓があります。
中世のとあるヨーロッパの町でのこと。旅人がある町を歩いていると、汗を流しながら、重たいレンガ積みを繰り返している3人のレンガ職人がいました。
旅人は「何をしているのですか?」と尋ねます。すると、その3人のレンガ職人は次のように答えました。
1人目は、「親方の命令でレンガを積んでいるんだよ」と答えました。
2人目は、「レンガを積んで壁を造っているんだ。お金になるからやっているのさ」と。
3人目は、「後世に残る大聖堂を造っているんだ。とても光栄だよ」と。
3人のレンガ職人は、それぞれ「レンガを積む」という同じ行為をしています。しかし、働くモチベーションがまったく違うのです。
1人目の職人には、希望や夢などはまったくありません。きっと生きるために必要だから我慢して働いているのでしょう。
2人目の職人には、お金という対価で得られる喜びはあります。しかし、働くことはあくまでも稼ぐことで得られる希望や夢のためです。
3人目の職人は、「後世に残る歴史的事業に参加している」という明確な目的意識を持って働いています。未来に大聖堂建設を完成させるという希望や夢のため、仕事を使命と感じています。
この寓話は、人のモチベーションが労働の効率性や生産性にどれだけ影響を与えるかという、教訓を示唆していますが、これはマーケティングの変遷にも通底しています。
「親方の命令でレンガを積んでいるんだよ」と言った職人は、労働をモノ消費しているにすぎません。
「レンガを積んで壁を作っているんだ。お金になるからやっているのさ」と言った職人は、対価としてお金という喜びに還元するコト消費をしています。
そして、「後世に残る大聖堂を造っているんだ。とても光栄だよ」と言った職人は、みんなで協力し合って労働すること自体に喜びを見いだすトキ消費をしているのです。
時代の変遷とともに、モノ消費が成熟し、コト消費からトキ消費へと移り変わる今日、テレワークやオンラインによるコミュニケーションが浸透していくにつれ、あらためてトキ消費の貴重性が実感されているのではないでしょうか。
ヒトが最も心を動かされるのはモノでもコトでもなく、ヒトと同じトキを共有体験することだと。
\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/
関連記事